吉濱ツトムさん④才能=楽しい、やる気になるのは間違い
吉濱ツトムさんの才能の発見の仕方は、これで最終話になります。自分にしかない才能を見出す方法をYouTubeにて述べられています。全4話シリーズで私自身とても共感することを話されていて、またそれを体験してみてとても良かったので、自分の思いも織りまぜながらまとめてみました。才能を発見するシリーズは、直ぐに実践できる内容になっていますので、この問題に直面している方がいらっしゃれば、お勧めします。また、これを読んで共感してくださったり、励みや勇気になったと思っていただければ幸いです。
これまでのおさらい
- 才能の特徴を知る
- 初めて取り組んだことにも関わらず何だか妙にうまい
- ソフト(習得の対象事)の吸収が早い
- 吸収したソフト(習得の対象事)を高速で高水準まで伸ばせる
- そのソフト(習得の対象事)を行う様が円潤で美しい
- 才能に対しての誤解を解かなければいけない
- 才能に対して持っている認識(後天的才能がすごいことなのではない)
- 才能の本来の真実(先天的才能)
- 才能があるがゆえに劣等感
- 細かい違いがわかる
- 自分自身のものに対しての問題点がわかる
- そのことに細かく分析できる
- 本当にいいものを良いと認識できる
- 良くも悪くも完璧主義
- 才能があるがゆえに否定する
「①自分にしかない才能を探す」についてはこちら↓
「②才能の価値を見出せない」についてはこちら↓
「③才能があると劣等感を感じてしまう」についてはこちら↓
こちらが今回の最終テーマ動画です↓
才能とワクワクする気持ちは違う
※太文字で書かれている部分は吉濱ツトムさんが述べていらっしゃる部分になります。
「才能が見つかったとしても、つまんない、あるいは無気力ですか?」世間一般のこたえとしては「むしろ才能が見つかったことによって自動的に走る、もしくは情熱を持って動くことができる」というのが大半ですよね。でも、それは間違いであるということ。確かに苦手なもの興味がないことをやるにはやる気だとか、楽しさっていうものがあるんだけども、そんな爆発的なものではないということ。理由として4つあって、1つ目は「才能があることであったとしても、仕事になるとそんなに楽しくなくなる」例えばプロ野球選手、彼らはとても楽しくやれているかというと決してそうじゃない。純粋に楽しくやっている人なんていうのはほとんどいない。実力は上がるが楽しくない。要因は多岐にわたるんだけれども一つとしては、仕事になると命をかけてやらないといけない。遊びでゲームをやっているんだったならば、楽しいじゃないですか。でもそれが、eスポーツみたいにそれで飯を食わなきゃいけない。あの人たち楽しいかっていうと決してそうじゃない。また趣味で文章を書いているのと、この文章を書かないと飯が食べれない、家賃が払えないとなると楽しいかというと楽しくない。超越したならそういったことを無視できるんだろうけども、あるいは結果を気にしないでやれるんだろうけども、人間っていうのは、どうしてもそこまで無視できない。要は生き残りがかかった瞬間に楽しくなくなっちゃうということ。仕事になることによって、急に楽しさが半減してしまうということがある。仕事になると、生き残りがかかっちゃうから楽しくなくなっちゃう。「才能とワクワクは違うということ」さっきの才能の特徴として、僕は独自固有の先天的長所ってよんで「初めて取り組んだことにも関わらず何だか妙にうまい」「ソフト(習得の対象事)の吸収が早い」「吸収したソフト(習得の対象事)を高速で高水準まで伸ばせる」「そのソフト(習得の対象事)を行う様が円潤で美しい」+(ワクワクって何ですか?というとそれに加えて)「いくら取り組んでも疲れない、疲れづらい」もしくは「疲れてとしても心地よさがある」ということ。2つ目としては、「途中過程に喜びを見出せる」ということ。3つ目「意識していないのにも関わらず、それに対して肯定的に積極的にあれこれ良くしようと考えなくても、ただアイディアが沸いてくる」ということ。4つ目「それに取り込んでいる最中に無条件に喜びだとか安心だとか、肯定的な感情が沸いてくる」こと。
- 才能の特徴を知る(独自固有の先天的長所)
- 初めて取り組んだことにも関わらず何だか妙にうまい
- ソフト(習得の対象事)の吸収が早い
- 吸収したソフト(習得の対象事)を高速で高水準まで伸ばせる
- そのソフト(習得の対象事)を行う様が円潤で美しい
+
- 才能の最終形態にあるワクワク
- 「いくら取り組んでも疲れない、疲れづらい」
- 「途中過程に喜びを見出せる」
- 「意識していないのにも関わらず、それに対して肯定的に積極的にあれこれ良くしようと考えなくても、ただアイディアが沸いてくる」
- 「それに取り込んでいる最中に無条件に喜びだとか安心だとか、肯定的な感情が沸いてくる」
確かに、こういう話は聞いたことがあります。好きな事をやっているはずなのに、自分が置かれている環境等の理由、利益(金銭的)のことを考えると途端にモチベーションが下がると・・・。私の体験においては、当時アロマサロンをしていたことです。他の人の体を癒すことができることは、とても好きで、価格にも拘ることなく低価格で提供していました。体力的には堪えますし、準備の時間と細かな配慮、丁寧さを必要とするお仕事でしたが、いつも程よい緊張感と充足感があり満たされるような感覚がありました。施術の準備をしている段階から、施術が終わるまでは、クラシック音楽を奏でているような感覚で事にあたっていました。しかし、家に帰るといつも「お金にならないよね」「価格設定もっとよく考えたら?」「まだ子どもが小さいし育児はそっちのけでいいの?」と、親や夫から散々言われていました。それも自営の経験がない人たちにです。でもその言葉が、自分でもどこかで思い当たる節もあったのでしょう。重くのしかかり、自分の中にあった才能とやる気のバランスを崩しはじめ、またそれと同時に、好きな事だけやって簡単に稼ぐということが、どれほど難しいことか、嫌という程味わいました。今あの時のことを全て理解した上で、再度アロマサロンを始動できるかと言われると、あの時のモチベーションが沸いてこないのです。情熱が見出せないのです。ただの趣味になってしまったのです。しいて言うならあの時に、親や夫に言い返すぐらいのメンタルがあればよかったのになって思います。やはり人生においては、才能の旬というものがあるのでしょうか。なので、これを読んでいる方の中で、今迷っている才能があるなら、旬が過ぎないうちに可能な範囲で開花させてほしいです。
才能を十分やり切った後に、初めてワクワクになる
これがワクワクなんだけども、このワクワクにいきなり飛び込めるかというと、大半の人は飛び込めない。というのは、例えば中核のワクワクがあったならば、いきなりそこを発見じゃなくて、糸にビーズを通すような形で小さいワクワクをこなしたら、次のワクワクがみつかって、更に次のワクワク、次、次、次、・・・・結果としてこの(中核)ワクワクになるということ。ということは、この中核の巨大なビーズのワクワクと、一番最初の小さなビーズのワクワクは、楽しさで比べたならば、こっち(一番最初のビーズ)は、ほんと小さいもの。巨象と蟻みたいなもんであるということ。だからこの小さなワクワクだとあんまり動くことができない。やる気にならないじゃないですか。実はこの才能っていうのは、一番最初のビーズに当たるということ。もちろん、相当離れた所じゃなくて、(中核から一番最初のビーズまでの距離)ここら辺にあるだろうけども。でも、残念ながらワクワクの途中過程に過ぎないということ。だから才能を見つけたとしても、やる気だとかワクワクだとか情熱そのものになるかというと決してそうではない。もちろん、才能を見つけたらいきなりどんぴしゃりのワクワク(中核)に行く人もいるんだけども、実はあくまでも「その才能っていうのは途中過程で、その才能を十分やり切った後に、初めてワクワクになることが多いということ。だから決して「才能=ワクワクだとかやる気、情熱」ではないということ。↓中核=㊥↓
才能≠ワクワクだとかやる気、情熱
〇〇〇〇〇・・・・・㊥
―――――――→㊥=ワクワク
途中過程で、その才能を十分やり切った後に初めてワクワクになる
楽しさの中にも恐怖心は存在する
仮にその才能が結構ワクワクとかぶっている、あるいは近かったとしても、否定的な感情が強いとそれが楽しめないということ。やはり人間の特徴って恐怖心ってのは極めて強い。その恐怖心が強いと、楽しさっていうのはかき消されちゃう。例えば、友達とビールを飲むことがワイワイガヤガヤやるのが好きであると、だけれども会社が倒産しちゃった、あるいは家賃さえ払えないって時に、これを楽しめるかっていう。楽しいことをやったとしても、人間というのは常にこっちに恐怖心がちらついてしまうということ。だから結果、「楽しむ、やる気」だとかっていうのを駆逐してしまうということ。もちろんどんぴしゃりのワクワク(中核)にはまり込んだならば、そういった恐怖心ですらも一掃できるんだけども、でも残念ながら強い喜びを見出せるわけじゃない。結果、恐怖心だとかあるいは普段の悩みだとか、あるいは反すう、否定的な思考をグルグル巡らしちゃう、っていうことに飲み込まれて、別にやる気だとか、楽しさだとか、情熱っていうのを感じられなくなりますよねっていう話であるということ。
「才能=楽しくない」は間違い「才能=苦手な分野よりは負荷がかからない」
才能があったとしても、自分から動くかというと決してそうではない。才能があったとしても実は嫌々やる。もしくはそんなに気乗りしない人が多いということ。言い換えると「才能=楽しくない、やる気がない」っていうのは間違いで、「苦手な分野、興味のない分野をやるよりはストレスがそんないかかりません。そんなにしんどくありません」っていうのが実態であるということ。だが世間一般では「才能=ワクワク、やる気になる、情熱がでる」っていう認識を持っているから、青い鳥症候群が山ほどいるということ。だからまず、そこの誤解を解かない限りは、才能を発見すること、あるいは、才能の最終的な形態であるワクワクを見出すことはできないですよっていう話になる。
才能=楽しくない、やる気がない
ではない‼
才能=苦手な分野よりはストレスがそんなにかかりません
※ここを理解した上で
↓↓↓
才能の先にあるワクワクを見出せる
まとめ
才能とワクワクする気持ちは違うということ、まず人は好きなことや得意分野を仕事のカテゴリにするから、生き残りやお金のためにという思いが溢れてしまう、でも働いて報酬を得るということが、社会の構造だからここは崩せない現実です。人は生活していくうえで、いや生きていくうえで、コミュニティー(家族・学校・職場等)に所属して、働いてお金を得ます。この世にお金というものが存在していなければ、人が生きていくうえでの学びの意味は、また違うものになっていたと思います。もし自分がお金の為ではなく働くという概念でもなく、ただ好きなことに熱中できる世界に生まれていたのならば、どうなっていたのだろうか。人としての進歩はあったのだろうか、争いは愚か「争い」という言葉自体生まれてこなかったのではないだろうか、お金からうまれる利害によって人は翻弄されているように思います。各言う私もその一人です。社会の構造として、2018年副業元年とも言われていましたが、現状はどうでしょうか。大幅に就業規則が変わることは難しいかもしれませんが、少しずつではありますが、変化はしていっていると思います。社会も変わりつつある中で、うまく自分の才能が発見でき、その後においての生き方があなたらしく創造できますように。
吉濱ツトムさんの「2040年の世界とアセンション」楽天ブックス電子書籍はこちらから↓
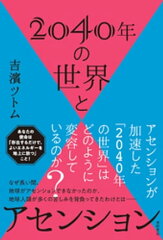 |
吉濱ツトムさんの「2040年の世界とアセンション」Amazon書籍はこちらから↓
吉濱ツトムさんの「2040年の世界とアセンション」楽天書籍はこちらから↓
|
|
最後までお読み頂きありがとうございます♡
読者登録・スターボタン励みになります♡
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/20635b1b.fa036716.20635b1c.913dd818/?me_id=1213310&item_id=20207484&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F2098%2F9784198652098.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
